tmPR(学生広報スタッフ)による教員インタビュー
interview
interview
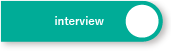 1
1

私が薬学部を受験しようと思ったのは、センター試験を受けた後のことでした。元々化学が得意だったことや、薬を使っていた経験から「薬って面白そうだな」と感じたことが、薬学部を選んだ理由の一つです。しかし、最も大きな決め手は就職先でした。
センター試験を受けるまでは、どの学部を受験するか迷っていましたが、色々な学部を調べる中で、本学の就職先に警察があることを知りました。ドラマや漫画などで見ていた鑑識や科捜研に興味があり、薬剤師だけではなく薬学に関連した就職先があるのを知り、「面白そうだ」と感じたことが薬学部を選んだ理由です。

一番の魅力は、伝統校であることです。これは実際に自分が薬剤師として働いてから感じたことですが、同窓生が多いため、どこ出身かという話になると、「東北医科薬科大学です」と答えると「自分も卒業生だよ」と言われたり、大学に共通する話題で親しくなれるきっかけがたくさんある点は、大きな魅力だと感じました。
また、一学年 200~300 人と学生数が多いため、部活やサークルへの参加、5 年次からの研究室配属などを通じて、大学内でさまざまな人と出会う機会が多いことも、本学の魅力の一つだと思います。現在は生命薬科学科や医学部もあるため、さらに多様な環境の人と出会う機会が増えていると思います。
さらに、大学に附属病院があることも、本学の大きなアピールポイントの一つです。附属病院があることで、5 年次の臨床実習をより充実させることができるようになりました。また、私たち教員も病院の薬剤部で研修を受けることがあるため、実務系の科目を担当している教員が病院業務を定期的に行うことができ、学生に今の臨床業務を伝えやすい環境が整っています。これも、本学の強みだと考えています。
クラスはとても仲が良く、みんなで飲み会を開いたり、コテージを貸し切ってキャンプをしたり、旅行に行ったりと、楽しい思い出がたくさんあります。写真は、四年生の時に参加した球技大会で撮ったものです。大会の約一ヶ月前からクラスの友人たちと集まり練習し、決勝まで進むことができました。決勝で負けてしまいましたが、それでも良い思い出の一つとなりました。

大学生活は今しかないので、勉強と私生活をうまく両立させて、楽しく頑張ることが一番大切だと思います。大切なのは、頼れるところは人に頼って頑張ることです。本学は学生数が多い分、同級生や先輩・後輩はもちろん、教員に頼ることもできる環境です。
大学時代の友人は一生ものの付き合いになると思うので、友人とのつながりも大切にしてください。時には、一人では頑張れないこともありますが、頼れる友人がいるだけで、やる気が出て頑張れることがあると思います。
また、個人的には薬学科であっても薬剤師という職業に固執しなくても良いと思います。大学に入ってみて、化学が面白いと感じてそのまま研究に進みたい人もいれば、さまざまな分野に触れるうちに、生物系などの分野に進みたくなる人もいるでしょう。しかし、医療人としての倫理観は絶対に持っていて欲しいと思います。薬学科や生命薬科学科、医学部も将来の夢として選択肢はたくさんありますが、最終的に医療に関係する分野に進むのであれば、薬剤師や医師になるかどうかに関係なく、医療人としての倫理観を大切にしてほしいと思います。

私は薬剤学教室という研究室に所属しており、臨床での経験と製剤学を生かした「医薬品」に関する研究を行っています。
研究テーマの一つに「配合変化」があります。配合変化とは、2 種類以上の薬を混ぜたときに生じる物理的または化学的な変化のことです。最近、在宅医療を利用する患者さんが増えていることを受けて、薬を長期間自宅で管理する際の影響を考慮して研究を進めています。これまでの研究では、配合変化が起こるかを 1 日などの短期間で観察していましたが、現在は期間を 3 日〜2週間に延ばして研究を行っています。
もう一つの研究テーマは「簡易懸濁法」です。この投与方法は、経口投与ができない患者さんに対して、経鼻や経口の経管チューブ、または胃瘻チューブを通じて、お湯で崩壊・懸濁させた薬剤を投与する方法です。これは薬剤が発売された際に想定されていた使い方とは異なるため、簡易懸濁法で投与可能な薬剤なのか、薬剤を崩壊させた後の安定性に変化がないか、また崩壊懸濁によって経管チューブが詰まることがないかなどを研究しています。一方で、簡易懸濁法の投与方法や可否の情報は成人向けがほとんどです。小児や乳幼児へは成人より細いチューブが使用されますが、細いチューブの薬剤通過性は少なく、さらに、小児でよく処方されている顆粒剤は、苦味のマスキングなどの観点からコーティングされているものが多く簡易懸濁法が難しい薬剤が多いなどの問題点があります。とはいえ、小児や乳幼児でも経口投与できない患者さんがいるため、そうした患者さんに対してスムーズに経管投与が可能な手法を可能にするための研究を進めています。
インタビュアー:tmPR 伊東 愛
他の教員の記事も随時更新していくので、アーカイブからぜひご覧ください。